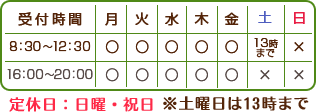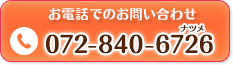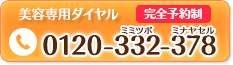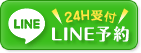少年野球肘の改善方法
2025年11月12日
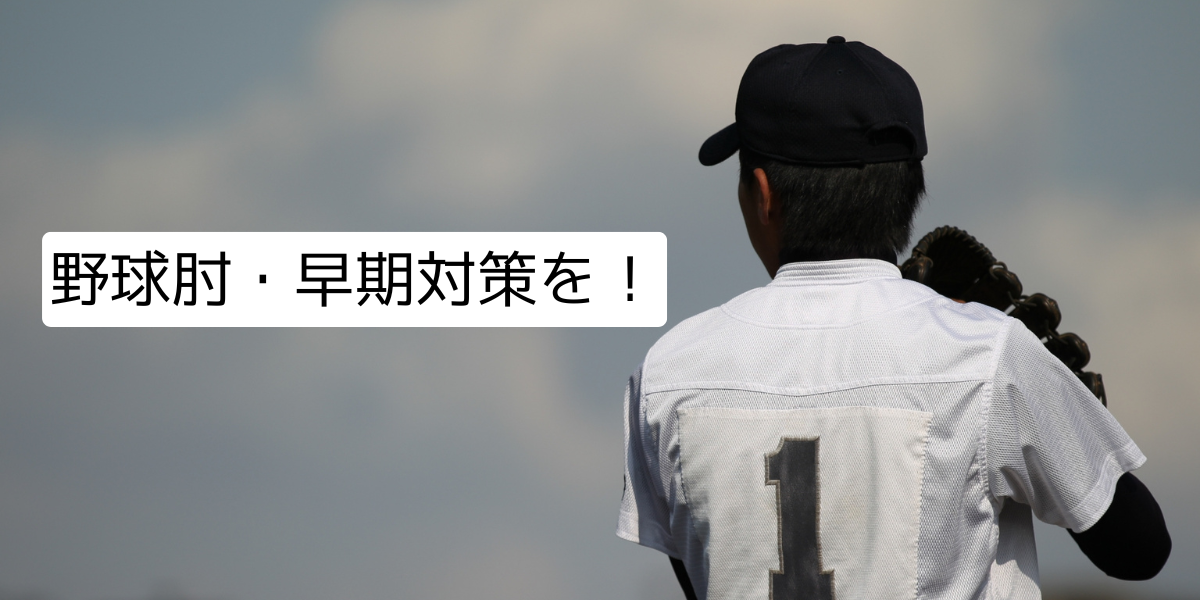
【野球肘とは?】
⚾️野球肘とは?成長期に多い投球障害の一種
野球に打ち込む学生や、野球チームに所属するお子さまを持つご家庭では、
一度は耳にしたことがある「野球肘」。
正式名称は「投球障害性肘関節障害」といい、
特に投手や捕手など、繰り返し投球を行う選手に多く発生します。
枚方市の「なつめ鍼灸整骨院」にも、
近年は野球肘に悩む学生や保護者の方からのご相談が増えています。
ここでは、野球肘の主な原因とその対策を、専門家の視点でわかりやすく解説します。
🩺野球肘の主な原因とメカニズム
以下の表は、野球肘の主な原因と特徴をまとめたものです。
肘の負担要因とそのケース
| 原因 | 内容 | 起こりやすいケース |
|---|---|---|
|
肘への過度な負担 |
投球時の繰り返し動作で関節や筋肉にストレスが集中 | 投手・捕手、投球数が多い選手 |
| 投球フォームの問題 | 下半身や肩の連動不足、アーリーリリースなどフォームが崩れやすい | 成長期選手 |
| オーバーユース | 投球制限を守らず連日練習 | 部活・クラブチームでの練習過多 |
| 成長期特有のリスク | 骨端線や軟骨へのダメージ | 小中学生、高校1年生頃 |
| 柔軟性・筋力不足 | 肩甲骨・股関節・体幹のアンバランス | 体幹トレーニング不足の選手 |
🧩原因①:肘への過剰なストレス
投球動作では、肘を高速で曲げ伸ばしするため、関節・靭帯・筋肉に大きな負担がかかります。
特に成長期の骨や軟骨はまだ未成熟で、負荷が蓄積すると炎症や損傷につながります。
💡代表的な障害:
内側側副靭帯損傷
内側上顆炎(いわゆる「ゴルフ肘」に近い)
🧩原因②:フォームの乱れ
-
肘が早く下がる「アーリーリリース」
-
下半身が使えていない
-
肩と肘の連動が不十分
こうしたフォームの癖は本人が気づきにくく、慢性的な負担を引き起こす要因です。
スポーツトレーナーや専門家によるフォーム分析・改善が欠かせません。
🧩原因③:オーバーユース(使いすぎ)
痛みを我慢して投げ続けることが最も危険です。
とくに成長期では、「離断性骨軟骨炎(OCD)」などの重症化を招くこともあります。
🩶なつめ鍼灸整骨院では
定期的な関節チェックで炎症や可動域異常を早期発見し、重症化を防ぎます。
🧩原因④:成長期特有の障害
成長段階では、以下のようなリスクもあります。
-
内側上顆骨折
-
外側骨軟骨損傷
-
骨端線炎(成長線の炎症)
なつめ鍼灸整骨院では、年齢・成長に合わせた施術と運動指導を行い、選手の肘を守るサポートをしています。
🧩原因⑤:筋力・柔軟性の不足
投球動作には「肩甲骨・体幹・股関節・前腕」の連動が不可欠です。
どれか一つでも硬いと、肘に負担が集中します。
当院では「メディセル筋膜リリース」を用いて、
筋肉と筋膜の柔軟性を高める施術と、自宅でできるストレッチ指導を行っています。
野球肘の予防・早期改善には対策が重要です。
🔹日常でできる予防法
-
投球数・練習量を管理する
-
正しいフォームの習得
-
毎日のストレッチと柔軟運動
-
アイシングで炎症を抑える
🔹整骨院での専門的なケア
-
鍼灸で炎症の抑制
-
骨盤矯正による身体の軸の安定化
-
メディセル筋膜リリースで関節柔軟性向上
-
投球フォームや身体の使い方のアドバイス
なつめ鍼灸整骨院(枚方市)での野球肘ケア
当院では、野球肘のリスクを最小限に抑え、選手が長く競技を続けられる身体づくりをサポートしています。
✅ 当院の特徴
-
スポーツ障害の知識に長けた国家資格保持者が施術
-
小中高生へ施術実績多数
-
筋膜リリース・骨盤矯正・鍼灸の総合施術
痛みが出た場合はもちろん、軽い症状のうちにご相談いただくのがベストです。
早期対策で、野球人生を守ろう!
野球肘は、決して珍しい障害ではありません。
正しい知識と早期の対応によって十分に予防・改善が可能です。
「まだ子どもだから大丈夫」と思わず、少しの違和感でも早めのケアが大切です。
枚方市周辺で野球肘に関するご相談があれば、
ぜひ「なつめ鍼灸整骨院」までお気軽にお問い合わせください。
未来ある選手たちのプレーを支えるお手伝いを、私たちが全力でさせていただきます!
【この記事を書いた人】
なつめ鍼灸整骨院 代表 溝口和也
明治鍼灸大学(現:明治国際医療大学)
平成13年鍼灸学士取得(第1670号)
国家資格:
柔道整復師:(登録番号:44703号)
はり師 : (登録番号:120047号)
きゅう師: (登録番号119965号)
得意分野:坐骨神経痛・むちうち・骨盤調整
【内容の最終チェック】
国家資格者が内容を確認し、最新の情報に合わせて随時更新しています。
最終更新日:2025年11月12日